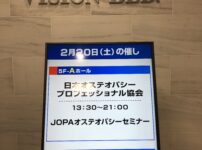鹿児島セミナー講師
セミナー終えて1週間が経とうとしていますが、コロナで遠方への移動は自粛していましたので、久々の飛行機は何か新鮮でした。 平日の昼間ですが、空港は緊急事態宣言のためか?閑散としていました。 今回は、鹿児島天文館にて2日館、JOPA主催の「脊柱と骨盤のモーションパルペーション」の講師をさせてただきました。 簡単にいうと、身体を診るための触診と評価を行うことです。 テクニックもせずに、2日間で述べ14〜15時間。 ひたすら座学と触診で受講生はかなりキツかったと思いますが、よく最後まで ...
ウィルス性の風邪にはオステオパシーが有効。
昨今、コロナウィルスの脅威が連日のように報道されています。 感染対策が重要なことは周知のことですが、自分の身体に対して注目されている方々は意外と少ない印象を受けます。 当院では、いわゆる「風邪」に対して免疫システムを活性化させることで、身体に侵入してくる有機物(ウィルス)に対抗させることが可能となります。 今回は当院で実施している三つの治療アプローチをお伝えさせていただきます。 ①粘膜の乾燥 この点においては、水分摂取や快適な湿度なども影響しますが、風邪のプロセスは粘膜の傷害から始ま ...
さらに解剖学!
今回も12月5、6日にJTOCにて解剖学の講義をさせていただきました。 そして今回で基礎医学の解剖学(筋骨格系)は全9回が終了しました。 思えばこの2ヶ月間は、解剖学のことや講義のことで追われていたように思います。 このブログの更新もかなり滞っていましたが、 今後徐々に再開していきたいと思います。 よく膨大な解剖学を学ぶことを揶揄する表現として、 「消防ホースから水を飲む」ような言い方を聞いたことがあります。 この表現を自分なりに解釈し理解すると。 水を飲むようにするには、飲め ...
再び解剖学!
久々の投稿です。 ここ最近はオステオパシーの学校の講師や、セミナーのアシスタントをさせていただく日が続いています。 今回も11月7.8日にJTOCにて解剖学の講義をさせていただきました。 私の講義では、「身体に触れること」触診の技術を深めていくことを主体にしています。 実際には、下記のように体の表面に水性マーカーで骨の輪郭を描いていきます。単純なようで、正確に骨の輪郭を描写するには、ある程度の触診能力や解剖学のイメージを必要とします。 生徒の皆さんには、その難しさを感じていただ ...
学びは深い。
しばらく定期的なブログ更新が出来ていませんでした。 久々の投稿での報告は、 今回 10月4・17・18日の3日間 神戸の住吉にて、ジャパントラディショナルオステオパシーカレッジ(JTOC)の解剖学の講義をしてきました。 私自身、JTOC二期生での経験を生かしてより実践をイメージできるように実技の時間を多く設定し、触診の重要性を第一に講義を構成しました。 またオステオパシーの哲学でもある、 「機能と構造は互いに関連する」 この言葉のイメージをいかに理解してもらえるかを念頭に講義を ...
筋肉の特性を知れば、運動が変わる。
今回は筋肉の特性ついてのお話。 普段の運動で感じる筋肉についての特性を知ることで、明日からの運動は確実に変わっていくと思います。今回は普段誰もが知るだけで運動が変わる方法を3つお伝えします。 ①温度が上がると筋収縮の効率が上がる 生理学的範囲内での温度上昇は、筋線維膜(筋細胞膜)の伝導速度増加させ、収縮速度を増加させ、筋が刺激される頻度を増加させます。これは発揮される筋力が大きくなることを意味しています。また温度が上昇すると、筋の代謝に関わる酸素活性が高まって筋収縮の効率が上がります。これを ...
靭帯と腱を理解する
関節が正常な生理的位置に戻るとすぐに、靭帯は結合組織の再生に要する3か月間に及ぶ治癒プロセスを開始する。 もしもこの期間中に再受傷しなければ、この関節に対するそれ以上の治療は必要ない。 Frank C, Amiel D 今回は靭帯や腱についてのお話。 私自身、昔は靭帯は自然治癒しないものと思い込んでいた時期がありました。 今回はそんな靭帯の特徴について、特に重要な点を3つご紹介。 ①靭帯が損傷する二つの要因 腱と靭帯では、持続的負荷によって破壊(損傷)する場合をクリープ破壊と言います。周期 ...
身体のつながり。「テンセグリティ」
「テンセグリティ」は姿勢に対する負荷、代償、適合、代償不全の影響を理解するのに重要な役割を果たす。 皆様はテンセグリティという言葉をご存知でしょうか? テンセグリティは、1929年に建築家のバックミンスターが「テンション(張力)」と「インテグリティ(統合)」を組み合わせた造語として提唱した概念で、身体の仕組みにもうまく応用されています。 以前から身体全体のつながりについては説明をしてきましたが、テンセグリティをより理解する事で、身体全体の構造が下記のような予測可能な反応を起こす事が理解で ...
オステオパシー的思考
「医師の目的は健康を見出す事である。病気は誰にでも見つけられる」ATstill オステオパシー的思考とは? オステオパシー医学を学ぶ学生たちが最初に学ぶことの一つに、目の前にある明らかな問題に集中するのではなく、むしろ不鮮明な部分に注意を向けなくてはならないという考えがあります。言い換えれば、「症状を治療するのではなく、原因を突き止めて治療しなさい」という事になります。 私は医師ではありませんが、下記のような例が分かりやすいかと思います。 COPD(慢性閉塞性肺疾患)の治療 ...
骨にとって極めて重要なこと
一つの骨の全てを完全に理解できれば、永遠の両端を理解したことになるAT still オステオパシーの語源はギリシャ語で「オステオン(骨)とパソス(病気)」という2つの言葉から作られた造語ですが、「骨の病気」を意味するのではなく、「骨の性質」に観点を置いた言葉です。 今回はその性質について重要な3つの点をお話いたします。 ①「骨は必要な部分で増加し、必要のない部分では再吸収される」Wolff 骨はある特性を持っており、応力(外力に対する内部の抵抗力)が存在することによって、骨は ...
身体からのメッセージ!
健康からの逸脱には原因があり、原因はある特定の場所に存在する。オステオパスの仕事はそれ(原因)を見つけ出し、取り除くことであり、病気を押しやり、健康を取り戻させることである。At.still 以前に「オステオパシーとは?」の説明にて、身体の構造に問題があれば機能にも問題が生じるといった考え方を説明させていただきました。では身体の構造はどのようにみていくか?今回は身体の構造における問題点の見つけ方についてのお話です。今回の内容を把握していただけることで、ご自身でもお身体の状態を確認することが可能になります ...